かねだ・けんや●1987年生まれ、兵庫県出身。小学生のころからパイロットになりたかったが、視力が足りず断念。かわりに航空関連の研究を志し、航空宇宙工学が学べる東京大学へ進学する。もともと得意だったシステム開発の経験を生かして、大学2年時に企業向け管理システムの開発などを行うための会社を立ち上げた。また、大学1年時に自分のためにつくった、スマートフォンで家電を操作するリモコンシステム「Plutoステーション」の商品化の際、2人の仲間と株式会社Plutoを設立する。2012年12月に発売された同商品は大きな反響を呼び、現在も量産を続けている。現在は東京大学大学院博士課程で人工知能について学びながら、Plutoに次ぐ製品の開発を行っている。

共同開発した市東(しとう)拓郎さんとの一枚。市東さんとは大学の先生の紹介で知り合った。「どの家電を動かすかを決めるところから、力を合わせて考えました」。
当たり前にやっていた「モノづくり」をビジネスに
システム開発を覚えたのは、中学の時に父親からパソコンをもらったのがきっかけです。あまりおもちゃやゲームを買ってもらわなかったので、「ならば自分でゲームをつくろう」と軽いノリで始めました。本やインターネットで調べながらプログラミング言語を勉強して、シューティングゲームなんかをつくって遊んでいましたね。完全な趣味です。誰につくってあげるとかではなく、自分でつくって自分で満足するだけ。今でも、「なければ自分でつくる」が当たり前になっています。
そうやってつくったモノで商売をしようと思ったのは、大学に入ってから。一人暮らしを始めてお金がなかったことと、何か面白いことを継続的にするためには、運営資金が必要だったからです。自分がつくったものを誰かが欲しがってくれるのであれば、値段がついてもいいのかなと思いましたし、お金を得る手段を仕組み化してもいいのかなと考えました。
最初に商品化したのが、企業向けの管理システムです。それを機に会社をつくりました。書類を提出して手続きをしただけ。取引先からの信頼を得るためにつくった会社で、「起業したぞ」なんて気持ちはまったくなかったですね。
「Plutoステーション(以下Pluto)」の原形をつくったのは、大学1年の夏ごろです。「Pluto」とは、スマートフォンを使って家電を操作するリモコンシステム。一人暮らしを始めたばかりで、真っ暗な家に帰るのが寂しくて(笑)、「家に着く前に明かりがつけられたらいいな」と思ってシステムを組んだのが最初です。これも自分のためにつくったものでした。
その後はオーディオやエアコン、テレビや洗濯機などが動かせるようになりました。朝になると自動的に音楽がなって、カーテンが開く。「こんなものがあったらいいな」を実現するためのモノづくりは、中学・高校の時にシューティングゲームをつくる感覚と同じでした。
商品化を思い立ったのは、今から3年ほど前。僕が最初につくったころに比べると、インターネットの通信速度が格段に速くなって、インターフェースとなるスマホが普及したことで、「もしかしたら欲しい人がいるかもしれない」と思ったからです。
最初にどの家電を操作するかを考えて、それに合わせて必要な部品をそろえ、コスト計算をし、家庭のリビングに置いたときに収まりのいいデザインの箱を設計。最後にシステムを完成させました。量産するための工場を探さなくてはいけなかったので、ネットや電話帳を使って日本中の工場を調べて電話し、CAD(設計支援システム)で描いた設計図を送って予算内でつくれるかをひたすら交渉です。最終的に1社見つかるまで、何社断られたかは忘れました。
一番大変だったのは、やはりシステムの設計です。リモコン信号のレスポンスのスピードを維持するためには、メンテナンスし続ける必要があり、そのためのシステムを事前に盛り込むようにしました。あらゆる不具合を想定し、それをクリアにするシステムをつくり続けるのは、思った以上に心が折れそうな作業でしたね。
でも、楽しいことはやめられません。つくりながら考えていたのは、「もっとワクワクしたい」ということ。というのも、本来、「家」という場所は、勉強や仕事が終わって帰るホッとできる場所のはずなのに、例えば「寂しい」「家族とうまくいかない」といったことでもし気が進まない場所になっているなら、それはすごくいびつだと思いました。
家具や壁紙は動かないし、好きなものを買って満足して終わりですが、家電は動くし、中にコンテンツが入っています。実はもっと人に影響を与えられるもので、人間関係が変わるとか、人生がワクワクするとか、そういうきっかけになり得るものではないかと考えていました。
もう一つ、「Pluto」は“人を選ばないプラットフォーム”になり得るのではないかということは常に考えていました。例えば、高齢者や障害者などの社会的なマイノリティ向けのサービスは、国の補助金を通してもたくさん提供されています。しかし、一般の人が当たり前のように使うものを、彼らも一緒に使うことができれば、マーケットそのものが大きくなるし、社会全体が豊かになり、高齢者や障害者の方々も助かるのではないかと思いました。そういう“人を差別しない”プラットフォームがつくれれば、大きな価値になると思ったのです。
その結果、発売してすぐに最初につくった400台は完売。すぐに量産しなくてはいけない状態に。どうやら口コミで広まったようですが、こんなに反響があるとはと、自分でも驚きました。

学業、仕事、遊びなどと分けず、面白いと思ったことをやり続けたい
現在は、大学院の博士課程で、航空宇宙関連の人工知能の研究をしています。システムで組んだ知能のモデルに対して、与えた特定の情報の処理内容をデータ化したり、仕組みの解析を行っています。一方でシステム開発の仕事は続けていますし、もちろん「Pluto」のメンテナンスもです。また、2014年に発売予定の、新製品の開発も進めています。
「Pluto」をつくったことで、モノづくりのハードルが下がったと思います。これまではただシステムをつくるだけだったのが、工場での量産というところまで挑戦したことで、次からは自分が当たり前につくれる領域が「量産する」ところにまで広がりました。次に何かをつくるときは、もっと楽にできるだろうと思えるんです。
基本的に「あれはあれ、これはこれ」という考え方なので、学業、仕事、遊びなどのくくりは気にせずに、面白そうだったら何でもやろうと思っています。面白いと思えることはいくらでも頑張れますが、つまらないことは頑張れません。だから、面白いことだけをやり続けるというのは、実は費用対効果がすごくいいんです。無駄なエネルギーを使わなくていいですから。
研究していることや、商品開発や会社運営の経験で得たことを将来にどう生かすかについては、まだ何も考えていません。これまでも、そして今も、面白いと思ったことをただやっているだけなので、先のことを考えて何かをするということができないんですよ。
僕はどこか「刺激オタク」な部分があるのかもしれません。時間があれば外に出て、空や海を見たり、美術館に出かけたり、自転車で旅行に行ったりして、いろいろなものに触れ、刺激を受けることが大切だと思っています。面白いものを一所懸命に探すというよりは、いろいろな経験をして、その中で面白いと思ったことはやる。面白くなかったらやらない。ただそれだけだと思います。
金田さんに10の質問
Q1. 血液型は?
A型です。自分でも几帳面な性格だと思います。
Q2. 趣味は?
Plutoもそうですが、自分で何かをつくるのが趣味ですね。料理もつくりますし、折りたたみ自転車も自作です(笑)。写真は友人にサプライズで誕生日を祝ってもらった際に、お返しにつくったペンケースです。

Q3. 好きな食べ物は?
焼き魚とみそ汁。基本的に、料理をするのが好きです。得意料理は…創作料理(笑)。
Q4.影響を受けた本は?
稲盛和夫『生き方』。あと、イギリスの生物行動学者・リチャード・ドーキンスの「The Selfish Gene(邦題:利己的な遺伝子)」です。
Q5.尊敬する人は?
北野武さん。彼の作品も、テレビでのコメントも、すべて本質を見ているところがスゴいと思います。
Q6.行ってみたい国は?
南極です。大の字になって寝転がって、ぼーっと空を見ていたい!
Q7. 100万円を自由に使えるなら何をする?
稼いで得たお金なら大切に使いますが、あぶく銭なら燃やしてみたい。とにかく、稼いだお金では絶対にしないことをしたいですね。
Q8.平均睡眠時間は?
毎日4時間から5時間くらいは寝るようにしています。
Q9. 宝物は?
自分の頭。なくなったら本当に困りますから。
Q10..座右の銘は?
「あれはあれ、これはこれ」
一日のスケジュール
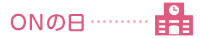

取材・文/志村江 撮影/刑部友康