かがわ・まなお●1993年4月16日、東京都生まれ。9歳の時に、友人が将棋をしているのを見て興味を持ち、その場でルールを覚える。強くなりたいと思い、親に直訴して近所の将棋クラブに通い始める。その後は将棋会館(東京都渋谷区)にある「将棋道場」に通い詰めるなどし、休日は朝から晩まで対局を重ねる。12歳で出場した「女流アマ名人戦」で初優勝。15歳で女流棋士に。高校入学後は女流棋士の活動を休場し、奨励会(※)所属となる。高校2年の2月に奨励会を退会し、女流棋士復帰。2013年10月に女流棋士・里美香奈さんを破り、第35期女流王将に。現在は立命館大学に通いながら、女流王将としてテレビ番組や将棋イベントなどに出演するほか、関西の若手棋士を中心に企画した「西遊棋(さいゆうき)」という将棋イベントの開催に尽力するなど、将棋界の発展のために幅広く活動している。
※:正式名称は「新進棋士奨励会(しんしんきししょうれいかい)」。プロ棋士養成機関の一つ

「西遊棋」のイベントを通じて、将棋をPR。将棋の魅力は「運の要素が少ないこと」と香川さん。「自分の決めたことが必ず結果につながります。責任が自分に跳ね返ってくるので、負けた時はすべて自分のせい。だから悔しいし、勝ったらものすごくうれしいんです」
将棋を始めて6年でプロデビュー。そこでぶつかった大きな壁
初めて将棋と出合ったのは、小学3年生の時です。友人の男の子がやっているのを見て、面白そうだと思ってルールを教えてもらいました。でも、覚えたてではまったく歯が立ちませんでした。それが悔しくて、勝てるようになりたくて、近所のおじいちゃんがやっている将棋クラブに通うようになりました。
私は飽きっぽい性格で、何かにはまってもそれほど長続きしないタイプでした。それなのに、将棋だけは飽きなかったんです。対局を重ねれば重ねるほど、友人たちには勝てるようになりました。けれど、おじいちゃんたちに強い駒を使わないというハンディをもらっても全然勝てません。自分よりも強い人がたくさんいて、上が全然見えない。だからこそチャレンジのしがいがあるし、頑張れば頑張るほど強くなれるというところが、とにかく面白かったんです。
転機となったのが、小学6年生の時に参加した「女流アマ名人戦」での優勝です。全国の女性の中でのチャンピオンという称号を頂き、すごく自信になりました。そして、アマチュアの世界から「プロ」という上の世界を意識するようになり、「育成会」という女流棋士になるための機関に入会しました。
今もそうなのですが、私の将棋はとにかく「攻め」のスタイル。どんどん自分からパンチを出していくタイプです。アマチュアの大会の決勝でも萎縮することなく、のびのびと自分好みの将棋を指せていたと思います。好きな将棋をしている時間がただ楽しく、とても順調でした。
プロになったのが中学3年生の時です。ただ、いきなり大きな壁にぶつかりました。それまでの「好きな手を選んで攻め続ける将棋」では、まったく勝てなくなったのです。当時の自分には、プロとしての力、そして自覚が、あまりにもありませんでした。
女流棋士になると、アマチュアの大会には出られません。トーナメント形式の公式戦は、負けたらその時点で終わり。せっかくプロになったのに結果を出せず、将棋が思うように指せなくなって、当時の自分は途方にくれてしまいました。
悩んだ末に、一度女流棋士としての活動を休場し、高校1年の夏に奨励会という別の育成機関に戻って修行を積み直しました。プロとして何もかもが足りなすぎると気づいて、もう一度勉強し直そうと思ったのです。ただ、奨励会は想像以上に厳しい世界で、努力しても努力してもうまくいかない自分にいら立つばかりでした。やはり思うように将棋が指せず、結果も出せないまま、高校2年の冬に退会。それから高校3年の12月まではどこにも所属せず、一人で気持ちの整理をしていました。
プロになるまでは本当に順調に来たので、壁にぶつかった時に、思うように解決できないことがすごく嫌だったんです。勝負の世界の厳しさを痛感した時期でした。そんな時に自分を支えてくれたのが将棋の先生であり、大学受験のために通っていた予備校や学校の先生たち。人生の先輩方でした。
はじめのうちはうまくいかないのは当たり前。次にうまくいくように努力することが大切なんだと。そういうふうに考え始めてからは、少し気が楽になりましたね。いろいろなことに挑戦して失敗して、それを積み重ねて成長していこうと考えられるようになり、プロの女流棋士としてもう一度きちんと歩んでいこうと覚悟を決めることができました。そして、それを具体的に「大学進学」というかたちで決断したんです。
立命館大学を選んだのは、将棋が盛んな学校だから。そして何より、関西というまったく知り合いのいない場所でゼロからスタートしようと思いました。一人の人としても成長したいという気持ちの表れでもありました。
頼れる人は誰もいないし、大阪にある将棋会館に行っても、知り合いは一人もいません。居場所がなくて寂しかったけど、そのたびに「自分で決めたことなんだから」と鼓舞していました。おかげで、積極的で粘り強い性格になりましたし、いろんなことに挑戦することが増え、自分で考える機会が多くなって、人間として視野が広がりましたね。結果的に、関西への移籍は“いい選択ができた”かなと思います。

強い棋士、魅力的な人間になりたい
大学に進学し、女流棋士として活動する中で、将棋への考え方も変わったように思います。勝てることばかり考える将棋から、「質を重視したプロの将棋」というものを意識するようになりました。
それは女流棋士として活動する中で、たくさんの方に応援をしてもらえるようになったからです。テレビ中継や新聞を通じて、私の将棋を見てくれる人がたくさんいるんだと意識するようになり、内容のあるいい将棋を指したいといつも考えるようになったので。さらに、自分らしさや個性を出していけたらいいなとも思うようになりました。強い棋士の方は皆、自分の個性や好みにとどまらない、美学や将棋観を持っているので、自分もそういうものを持って戦いたいと思っています。
大学に入った時に、最初に掲げた目標が「タイトルをとる」ことでしたが、2013年10月、大学2年生で女流王将のタイトルをとれたことで、一番の夢がかないました。
女流王将とは、6つしかないタイトルの一つですから、重みがあります。少なくとも一年間はトップの一人として活動することになりますし、責任も大きいです。将棋の普及のためにイベントやテレビに出ることも増えました。注目されるので、それ相応の振る舞いを求められます。例えば人前に出る時にはちゃんとした話し方ができないといけないと思い、大学では言語コミュニケーションという専攻で、音声表現の講義を受けたりしていますね。
最近は普及もよりいっそう頑張らなくてはと思い、関西の若手棋士同士で「西遊棋」という、将棋に親しんでもらうためのイベントを企画したりしています。当然学校の単位もとらなくてはいけませんし、毎日時間をつくるのに苦労しています。それでも魅力的な人間、理想の棋士になるために、いろいろなことに挑戦するのはとても楽しいですね。
こうして私が女流棋士として活動できているのは、いろいろな方の支えがあってこそです。将棋界、具体的には棋戦やイベントを支えてくれるスポンサーの方々や、楽しんでくれるファンの方々。個人的にお世話になった師匠や先輩、学校の先生や家族も含めて、周りの人たちにはいつも感謝の気持ちでいっぱいです。もちろん、今年の女流王将の防衛は大きな目標です。ただ、自分の夢を勝負だけにとどめたくありません。少しでも多くの人に向けて、将棋を知るきっかけをつくることや、将棋のよさ、将棋を通じて何ができるかを伝えることが、今の自分がやるべきことだと思いますし、やりたいことでもあります。そうした貢献が、支えてくれる皆さんへの感謝のかたちの一つになるのではないかと思っています。
香川さんに10の質問
Q1.好きな異性のタイプは?
私にないものを持っている人。あとは、好奇心旺盛な人にひかれます。
Q2.趣味は?
語学の勉強です。フランス語がしゃべれるようになりたい!
Q3.好きな音楽は?
倉木麻衣さんが好きです。広瀬香美さんの『ゲレンデがとけるほど恋したい』も好き。
Q4.好きな映画は?
最近見たのは『トリック劇場版』。阿部寛さん、かっこいいです。
Q5.100万円を自由に使えるとしたら?
宝くじ(笑)。
Q6.行ってみたい場所は?
国内なら地方に出かけて、その土地のおいしい料理を食べたいです。
Q7.好きな場所は?
実家のある東京都調布市。東京なのに緑が多くて、川が流れていて、静かで落ち着くんです。月に一度は実家に戻って、のんびりする時間をとるようにしています。
Q8.好きな食べ物は?
甘いものが大好きです。写真はクレープですが、一番好きなのは、ショートケーキ!

Q9.リラックスするための方法は?
人と話すのが好きなので、友達とお茶に出かけて、気が済むまでおしゃべり(笑)。
Q10.座右の銘は?
「執念」。これだけは譲れない、自分はこれがしたいんだという「執念」こそ、自分自身のことを引っ張ってくれる一番の武器だと信じています。
一日のスケジュール
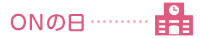

取材・文/志村江 撮影/刑部友康