わたなべ・なつひこ●1995年6月26日、東京都生まれ。6歳年上の兄がサッカーをしていた影響で、物心ついたときからサッカーに親しむ。初めてボールを蹴ったのは2歳の時で、本人いわく「誰に教わるでもなく、体でサッカーを覚えた」。小学3年生の時にクラブチーム「FCトリプレッタ」に入り、中学時にはキャプテンを務める。その後、サッカーの強豪校の一つである國學院久我山高校(東京)に進学し、1年時に全国高校サッカー選手権に出場。そこでのプレーを高く評価され、U-17日本代表に選出。3年時はU-18日本代表候補となる。また、キャプテンとして再度、全国高校サッカー選手権に出場。チームは惜しくも初戦敗退するも、2014年4月からドイツで開催される「デュッセルドルフ国際ユースサッカー大会」に出場する日本高校選抜チームのメンバー18人に選ばれる。14年、AO入試で慶應義塾大学に合格し、卒業後のプロ入りを目指しながら部活に励むとともに、スポーツビジネスを学んでいる。

高校3年時の全国高校サッカー選手権は、初戦で敗退。「将来、あの時に負けてよかったと振り返れるように、悔しさをバネにさらに上を目指したいです」。前列中央が渡辺さん。
「なりたい自分になれるように、しっかり勉強しよう」と常に考えていた
6歳上の兄の影響で、物心ついたときからサッカーが生活の中にありました。幼稚園の年少組の時に初めて近くのスクールに入り、小学校3年生で「FCトリプレッタ」という地元のクラブチームに入会。そのころにはもう、はっきりと「将来はプロのサッカー選手になって活躍したい」と真剣に思っていました。ただプロになるだけじゃなく、ちゃんと活躍できる選手になろうと、具体的に考えていました。
今の日本でプロのサッカー選手になろうと思ったら、Jリーグのチームが運営する下部組織に入って高いレベルで練習を積む方法と、高校サッカーで活躍して評価される方法があると思います。僕も、プロに近づくために前者の道を考えたこともありました。ただ、サッカーは大好きだけど、サッカーだけじゃなく、学校の勉強は勉強でしっかりやりたいという気持ちも強く持っていたんです。
もちろん、目先の目標はプロの選手ですが、一方で「その後」という視点も自分の中にありました。自分のやりたい仕事をしたい、そのためには「なりたい自分になれるように、しっかり勉強しよう」ということを常に考えていたんです。勉強しておけば、将来選択できる道が広がるはずだと。きっかけは特になく、自然とそう考えるようになっていました。
そんな僕に合っていたのが、國學院久我山高校。まず、サッカーのスタイルが自分に合っていると思いました。具体的には「自分で考えて、自分で判断するサッカー」で、結果的にはパスサッカー(パスでつなぐ戦術)につながることが多いのですが、スペインのFCバルセロナというチームのような、やっていても、見ていても面白いサッカーです。そして、サッカーだけでなく、勉強の面でも高いレベルで学べる環境がありました。この2つが高いレベルで両立できるところは、全国的に見てもほかにはないと思い、進学を決めたんです。
自分のイメージでは、最初の2年間は必死に頑張って練習し、3年生で全国高校サッカー選手権に出られたらいいなと思っていました。ところが1年から試合に出ることができ、しかも全国選手権にも出られ、さらにU-17の日本代表にまで選んでいただいた。僕は本当にラッキーだと思っています。
3年生になってキャプテンを任されてからは、「一体感のあるチームを作ろう」といつも心がけていました。サッカーの面白さの一つに、「気」というものがあります。試合の苦しい場面で11人の選手がピッチの上で必死に戦っているときに、ベンチや応援席にいるメンバーが同じ気持ちでいられるかどうかは、試合結果をものすごく左右します。
サッカー部員は全部で160人もいたので、トップチームの30人と、その下の130人に分かれて練習や試合を行います。僕の役割は、この30人と130人を一つにすること。それがチームの一体感を高め、強くすることだと考えました。そのために、トップチームの試合でも、その下のチームの試合でも、どの試合も全員で応援に行き、全力で応援するようにしたんです。また、選手権の前には僕自身が率先して「僕たちの持ち味は一体感。常に160人で戦えるチームなんだ」とメディアに話しました。
夏のインターハイの東京都決勝は、終盤まで劣勢の苦しい試合展開。しかし残り数分のところで、授業を終えた130人が駆け付けて、ものすごい勢いで応援をし始めたんです。その時に、「これは勝てる!」と感じました。そして実際に、最後の最後で逆転して全国大会に出ることができました。この時は、「誇らしい、いいチームができたな」とうれしく思いましたね。
僕たちのチームのスタイルは、相手チームは関係なく、自分たちのやりたいことをやるサッカーです。相手が僕たちを研究してきて、いろんな方法で崩してくることをわかったうえで、「だったらいつもと違う動きをして、スペースがうまく作れたらそこを使って試合を作ろう」などと考えながらプレーします。
ところが、最後の全国高校サッカー選手権では、相手チームに先制されたことで、僕自身も含め、みんながものすごく焦ってしまって初戦で敗退することに。試合後のインタビューでは「90分間冷静に、普通にできた」と答えたのですが、本当はそんなことはなく、あんなに焦って思うようにできなかった試合はなかったんです。大事なところで自分たちのやりたいことができなかったら、それは何も意味がないと思いました。本当に悔しかったし、自分たちはまだまだだと思いました。

いろいろな選択肢を考え、それを実現できる人間になりたい
僕の最終的な目標は、「日本代表のサッカーチームを世界一にすること」。そのために何をやるべきなのかは、今はまだわかっていません。僕が選手として活躍したり、指導者になって後進を育てる方法もあると思いますし、サッカー協会に入って改革していく方法もあるかもしれません。また、これはAO入試の時にテーマにもしたのですが、何かしらの組織を作り、指導者の育成をしていく方法もあると思います。
そのように、何事に対してもいろいろな選択肢を考えられる人間になっていたいです。同時に、考えた手段を自分で実現していける人間になりたい。そのためには、いろいろなことをたくさん勉強しなくてはいけないと思っています。
大学で学びたいことの一つが、「スポーツビジネスと育成」というテーマです。今の日本のサッカーにおいて、世界と比べて何が劣っているかを考えたら、選手育成ではないかと考えています。海外ではうまくいっている国がたくさんあるわけですから、ほかの国がどんなことをしているのか研究し、日本の特徴に合った形で取り込んでいける方法を考えていけたらいいなと思って。だから、スポーツビジネスを研究し、経営戦略やコーチング理論、心理学や世界の文化、もちろん言語についても勉強したいと考えています。
学んだことのすべてが必ず生かせるとは思いません。その中から必要だと感じたことがあれば生かせばいいし、さらに勉強が必要なことがあれば、そのときに学んだらいい。「今、やりたいことを全力でやる」という気持ちは、常に忘れずに持ち続けていたいと思います。
U-18の日本代表候補になった時に、1週間という短い期間で、そのチームに必要とされる選手になることの難しさを感じました。自分のいいところを残しつつ、環境に合わせて自分を変えていくのは、難しいことだけど、すごく重要なことだと痛感しました。高いレベルでそういう経験ができたことは、今後の人生において大きな財産になったと思います。
もちろん、プロの選手になって活躍することが、今一番目指していることです。まずは大学で、高校の時に果たせなかった日本一を目指したい。そして、もっとサッカーがうまくなりたいです。
渡辺さんに10の質問
Q1.好きな異性のタイプは?
一緒にいたいと思えて、そばにいると心の底から落ち着く人です。
Q2.趣味は?
お風呂に入ること。遠征であちこちに行くので、いろいろな温泉に入るのは楽しみの一つですね。
Q3.好きな映画は?
名作と言われるものはできるだけDVDで借りて観ようと思っています。好きな作品を一つ挙げるなら『Good Will Hunting』。最近観て面白かったのは『ムーンライズ・キングダム』です。
Q4.好きな食べ物は?
お寿司です。好きなネタは、小さいころからずっと変わらず「サバ」です!
Q5.100万円を自由に使えるとしたら?
旅行。サッカー遠征でスペイン、ブラジルなどに行きましたが、ブラジルはもう一度行きたいですね。あと、時間があれば、バックパッカーで世界一周したい。写真はスペインに短期サッカー留学に行った時のものです。

Q6.尊敬している人は?
両親です。父親は好きなことを仕事にしているので、自分もそういうふうに生きていけたらいいなと思います。母親は、とにかく無償の愛ですよね。毎日僕のためにお弁当を作ってくれるなど、ただただ感謝の言葉しかありません。
Q7.会ってみたい人は?
サッカー選手なら、FCバルセロナのアンドレス・イニエスタ選手。一緒に写真を撮ったり、ボールを蹴れたりできたら最高ですね! あとは、元陸上選手でスポーツコメンテーターの為末大さん。彼の本『インベストメントハードラー』(講談社/税抜き1600円)にはとても影響されました。
Q8.自分を動物に例えると?
ネコの自分勝手で自由気ままなところが、自分と似ていると思います。
Q9.宝物は?
試合中以外はいつも着けているネックレスです。両親にもらったもので、身に着けているだけで安心できるからです。
Q10.座右の銘は?
志高頭低。字のごとく、そういう人間でいたいといつも思っています。
一日のスケジュール
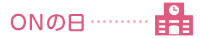

取材・文/志村江 撮影/刑部友康