
大会のプレゼンテーションはすべて英語。「英語は得意ではなかったので、やり遂げられたことは大きな自信になりました。おかげで、ゼミや卒業論文の発表のときはほとんど緊張しませんでしたね(笑)」。
「やらずぎらい」は嫌! 挑戦してから判断したい
「経営システム工学科」に興味を持ったのは、高校時代に「株主優待」というものを知ったことがきっかけです。友人がハンバーガー店の優待券を持っていて、そんなものがあるのかと興味を持ちました。自分で調べてみたところ、身近で面白そうなテーマで勉強のしがいがあると感じたんです。そこから、株や投資など金融について学んでみたいと思うようになりました。
大学4年になり、僕自身は大学院に進むつもりだったのですが、周りの友人たちは就職活動を始めていました。それを見ながら、「僕も来年はやるから」と、興味のある仕事について考えてみたんです。そこでふと思い浮かんだのが「証券アナリスト」という仕事。いろいろな理論を駆使して企業について分析するなんて、なかなか面白そうだと思いました。そんなことを考えている時に、たまたま研究室の先生から紹介されたのが、「CFA Institute Research Challenge」という“企業分析力を競う”大会でした。
一般社団法人のCFA協会が主催していて、毎年異なる対象企業について大学生が分析し、レポートとプレゼンテーションの内容を競う国際大会です。聞いたときには、「こんな大会があるんだ」と思いました。そして、「企業を分析するって、実際にどうやるんだろう?」と興味がわいたんです。
僕はもともと、「やらずぎらい」というのが嫌で、どんなことでもやってみてから判断したいタイプ。最初からやらないという選択肢をとることで、自分の可能性をせばめたくないのです。興味のあることでもあったし、せっかく先生が教えてくれたので、挑戦してみようと手を挙げました。
とはいえ、いざ取りかかったら、これがものすごく大変で。分析するのは好きだからと考えていましたが、甘かったですね。2011年の大会に出た先輩のアドバイスで、過去のレポートを読んだのですが、「これは自分には書けない!」というのが第一印象。本当に細かく分析されているし、将来の予測もきちんとされている。しかもそれを短くわかりやすくまとめている。やると言ったものの、最初は不安しかありませんでした。
分析対象となる企業が発表になり、実際に分析作業に取りかかり始めたものの、授業で学んだどの理論をどう使うかというところから考えなくてはいけません。一応、「SWOT分析」(※1)または「5forces分析」(※2)、「DCF法」(※3)という企業分析のための理論を使うことが必須で、必要なら「マルチプル法」(※4)や「同業他社比較法」(※5)等のvaluation手法を取り入れてもいいとの設定がありました。それらを基に分析方法を組み立て、研究室の先生や、メンターである証券アナリストの方に相談して進めていったのです。
※1)事業環境変化に対応した経営資源の最適活用を図る経営戦略策定方法の一つ。
※2)業界の収益性を分析する手法の一つ。
※3)収益資産の価値を評価する方法の 一つ。
※4)収益性類似企業と比較して企業価値を測定する方法の一つ。
※5)企業価値を測定する方法の一つ。
企業データを集めて分析していく中で、分析対象企業がグローバル展開をしているという点に注目し、世界の各地域ごとにライセンス契約社数を調べ、平均売上高を計算。そこから、将来の売上高予測を立てていくという方向性で勝負しようとまとめました。ここが、最も力を入れたところです。
最初のレポート審査では、資料の完成が締め切りの2分前。ギリギリ間に合い、何とか通過することができました。続くプレゼンテーションは、英語で。正直、僕らのチームは英語があまり得意ではなかったので、本当に苦労しました。受験勉強のときの教材を引っ張り出し、英語に慣れるところから開始。プレゼン内容はすべて丸暗記です。分析に費やす時間と同じくらい、英語での準備に時間がかかったと思います。
プレゼンテーション当日は、手応えなどまったくありませんでした。質問されたことに対してストレートに答えきれず、違う内容について説明してしまうなど、なかなか思うように発表できませんでした。結果が出る直前に、4人で先生とメンターの方に謝ったくらい、あきらめていたのです。だから、優勝と言われた時は信じられませんでした。しかも、審査員3人一致での結果と聞き、驚きました。力を入れて取り組んだ売上高予測を含むvaluationの部分を評価されたとわかり、うれしかったのですが、その後の総評では「優勝チームはプレゼン資料が貧弱ながら…」と言われてしまい、思わずずっこけてしまいました(笑)。

何かをちゃんとやりきることができれば、進むべき方向に進んでいける
「CFA Institute Research Challenge」への参加を通じて、社会を知ることができたように思います。証券アナリストとして働くメンターの方への相談を通じて、分析のプロがどういう手法で、どうやって物事を考えながら仕事をしているのかを間近に見ることができました。自分たちなりに分析を進めたことと相まって、物事への視野が広くなり、とても勉強になりました。
また、授業で教わった分析手法などの理論についても、理解が深まりましたね。実際に使うとなると、ちゃんとわかっていなければ使いこなせませんから、必死で勉強。実際に分析で使ってみて、その方法論の奥深さや面白さに気づくこともありました。
一方で、興味があった証券アナリストという仕事に対しては、「本当に自分にできる仕事なのか?」と考えるようになりました。今回はチームで力を合わせて企業分析をしましたが、これをすべて一人でできるのだろうかと。もっと自分に合う仕事があるかもしれない。そう考えるようにもなったのです。
両親からの教えの一つに、「縁のあるところに進んでいく」というものがあります。何かをちゃんとやりきったら、その次には必ず、縁のある方向に進んでいくことができるという考え方です。今回のCFA Institute Research Challengeは、参加するべくして参加したのではないかと思うことがあります。そして、就職についても、今は具体的には何も決めてはいませんが、いろいろなことに挑戦し続けていれば、何か縁のある方向に進んでいけるはずだと思っているんです。
CFA Institute Research Challengeにチャレンジして一番よかったことは、「無理だ、嫌だ、できない」と思っていることでも、やってみたら面白さに気づけるかもしれないと学べたこと。前から自分の中にあった「やらずぎらいにはなりたくない」という気質がいっそう強くなったように感じます。
人はよく、未経験だけど嫌なことについて話すときに、「○○だと思うから嫌だ」と言います。必ず「だと思う」というのがつくんです。「○○だから嫌だ」と断言できる人って、少ないと思います。やらずして「嫌だと思う」からやらないなんてもったいないと思いませんか? 僕は、自分の意思で、積極的にいろいろなことに挑戦していきたい。サークルの練習も、大会も、バイトも、そして勉強も。どれも手を抜かず、バランスを取りながらやり抜きたいと思っています。
渡邊さんに10の質問
Q1.好きな異性のタイプは?
僕が人見知りなので、積極的に話してくれる人の方が接しやすいですね。あとはもう、好きになった人が好きなタイプです(笑)。
Q2.趣味は?
テニスとスキューバダイビングで体を動かすのが好きです。でも、ゲームも大好きで、休日は家でずっと「パズドラ」とかをしています。
Q3.好きなアプリは?
最近、携帯電話でダウンロードした「速攻!1日1分で身につく!自分の能力を引き出すメンタル強化術」(400円)というアプリは、物事を原因から考えるという点で、とても参考になりました。ものの考え方を探るような本に興味がありますね。
Q4.好きな食べ物は?
学校の近くにある「凌駕」というラーメン店の、ゆずのつけ麺。ラーメンは好きで、昼食、夕食問わずよく食べますね。
Q5.100万円を自由に使えるとしたら?
サークルや免許合宿の費用として両親に借りていた分を返却し、夏のスキューバダイビングやテニスの合宿費用に少し取っておき、残ったお金で「投資」に挑戦してみたいです。研究はしているものの、まだ実際にやったことがないので…。
Q6.尊敬している人は?
父親です。いろいろなことを知っていて、何を聞いても教えてくれます。本当の意味で頭がよく、周りに人が集まる人なんです。自分が父親の年齢になったときに、同じような人間になれるかなと、いつも考えていますね。
Q7.会ってみたい人は?
テニスプレイヤーの錦織圭さんと松岡修造さん。僕はテニスをやってきたおかげで、いろいろな人と出会えたり、普通じゃなかなかできない経験もさせてもらいました。勉強などほかの活動もテニスのおかげで頑張れたと思っています。だから世界で活躍している2人にも「テニスをやってきてよかったこと」について聞いてみたいです。
Q8.好きな場所は?
海の中です。ダイビング中は、その幻想的な雰囲気に包まれるだけで気持ちも落ち着きます。

Q9.行ってみたい場所は?
パラオの海がきれいだと聞いたので、潜りに行ってみたいですね。実は海外に行ったことがないので、もっといろいろな場所の海を見てみたいです。
Q10.座右の銘は?
「今を楽しむ」。高校までは、先の人生を少しでも楽しくするために努力を続けてきました。でも今は、その時を全力で楽しみたいと思っています。本当に楽しむためには、“楽”をせずに努力することが必要なんですよね、何事にとっても。これからも目標を持って“楽しんで”生きたいと思っています。
一日のスケジュール
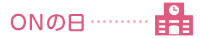

取材・文/志村江 撮影/刑部友康